
Wedding-UP DAY
2025.07.18
納得を生み出す共創をつくるミライへ。結婚式が『四方よし』を叶えるためには|Wedding-UP DAY 2025【関東編】
2025年1〜2月に全国5エリアを対象にオンラインで開催した「Wedding-UP DAY 2025」。時代と共に移りゆくカップルのニーズとウエディングの本質的価値を捉え、社会が必要としているウエディングのあり方を式場各社と共創していきたいという想いのもとに開催されました。
第1部ではマーケティングトレンド勉強会を、第2部では各地の事業者様と共に特別クロストークセッションを実施し、業界全体が社会視点で課題を捉え、カップルだけでなく働き手も幸せになる「四方良し」の未来を考え、共に語り合いました。
今回は、2月15日に開催された関東編の第2部で株式会社八芳園 取締役総支配人 関本敬祐氏を迎えた、特別クロストークセッションの模様をお届けします。
■登壇者プロフィール
スピーカー:
株式会社八芳園 取締役総支配人 関本敬祐氏
株式会社ウエディングパーク 松尾 美緒
ファシリテーター:
株式会社ウエディングパーク 金 小熙
「結婚式への評価は高い」 社会からみた結婚式の「イマ」
関本氏は、社会の視点から見る結婚式の現在について、「ウエディング業界全体に対しては実施率の低下が見られ、明るい話題は少ないように思います。しかし、現場での実感としては、ウエディングへの評価は低くなく、むしろ良いと感じます」と分析。その理由として、結婚式場探しではクチコミや親のおすすめを重視する人が多いことを挙げました。
「結婚式への評価が高いからこそ、人づてにすすめられます。また、新規参入や開業も一定数ありますが、業界全体に課題があるというより、価値観をどうとらえ直すかが課題であると考えています」(関本氏)
ウエディングパークの金は、同社に寄せられるクチコミは肯定的なものが多く、Z世代向けの調査では「約5割が結婚式に前向きだった」と報告。一方で、Z世代は「自分らしさ」を求める傾向があり、それぞれの形が見えにくく、不安に感じる方も多いと指摘しました。
「見えやすくすることにはメリットとデメリットがある」と関本氏は指摘します。「結婚式は、事前にすべての内容が見える形で購入するものではないため、安心感が重要です。今、課題なのは事業者が考えているウエディングの価値観と、カスタマーが求める価値観のズレです。どこが一致していないのか可視化することが重要です」と強調しました。
ウエディングパークで結婚式における費用の透明化を目指すサービス「mieruupark」の責任者を務める松尾は、関本氏の指摘に共感し、「現在、社会から求められている要素の一つに、安心感や納得感があります」と語ります。

左からウエディングパーク金、八芳園 関本氏、ウエディングパーク松尾「カップルと式場の間に情報のギャップがあり、それを解消することが大切です。結婚式の費用がすべてオープンになればいいわけでもなく、費用を上げることが悪いことでもありません。mieruuparkの顧客調査では、『費用の透明性は嬉しいが、それ以上に式場のスタンスや姿勢に感動した』という声もあります」(松尾)
金はSNSの台頭により、ユーザーが得られる情報が増え、スタッフとカップルの間で情報のギャップが生じるケースがあると指摘します。現場について問うと、関本氏は「大いにある」と回答しました。
「事業者は自社の式場については把握していますが、マーケット全体をとらえきれていないことも少なくありません。しかし、お客様はマーケット全体を見ながら、流行についての情報を持っています。情報収集の仕方が全然違うこともあり、ギャップが生じているのは事実です。そのギャップをどう捉え、どのように対応していくかが重要です」(関本氏)
松尾は「世の中の変化としては、結婚式に触れる機会が減少しており、参列経験も少なくなっています。昨年、私も結婚式を挙げた際に『初めて結婚式に参列した』という声を多く聞きました。これから挙げるZ世代以降の世代は『そもそも、結婚式って何だろう』という基本的な情報から必要となり、ウエディング業界とのギャップが広がることが予想されます」と指摘しました。
今の世代と価値観を擦り合わせる方法として、八芳園はSNSを活用しており、利用者の選択基準は従来とは異なると関本氏は語ります。

「多くのお客様は、まずSNSで投稿された情報を見て、その画像から『このフォトグラファーに撮ってほしい』と撮影者を指名し、その上でウエディングプランナーに相談されます。従来の打ち合わせの形式では対応できませんでしたが、お客様が自由に選べる環境がベストなので、仕組みを変えていっています」(関本氏)
さらに、今のお客様は会場側のレールが見えた瞬間に納得しにくくなると指摘します。そのため、要望に沿えない場合でも、誘導するのではなく理由を説明し、代替案を提示することで納得感を生み出しています。
社会からみた結婚式の「ミライ」~ウエディング業界の変化と情報の透明性とは
業界が変化すべき点の一つとして“透明性”があると提案した金に対して、関本氏は「業界全体でガイドラインを策定し、情報の透明性を担保しようとしても、それだけで透明になるわけではありません。また、現状でも情報の正確性や量に混乱するお客様が多いです」と述べます。「その結果、ウエディングの価値観が損なわれたり、場所や日にちだけで選ばれる無個性なものにならないよう、お客様が納得できる形をつくらなければなりません」と語りました。
松尾もユーザー調査の結果から、「正しい情報がわからないまま式場選びをして迷っている方が多い」と同意しました。
「情報が多ければ良いわけではなく、ユーザーが想像しやすい、わかりやすい情報をどう届けるかが重要です。SNSで調べたときに視覚的にわかりやすく、さらにその背景にある思いが知れ、共感が生まれるような情報を盛り込むことが大切です」(松尾)
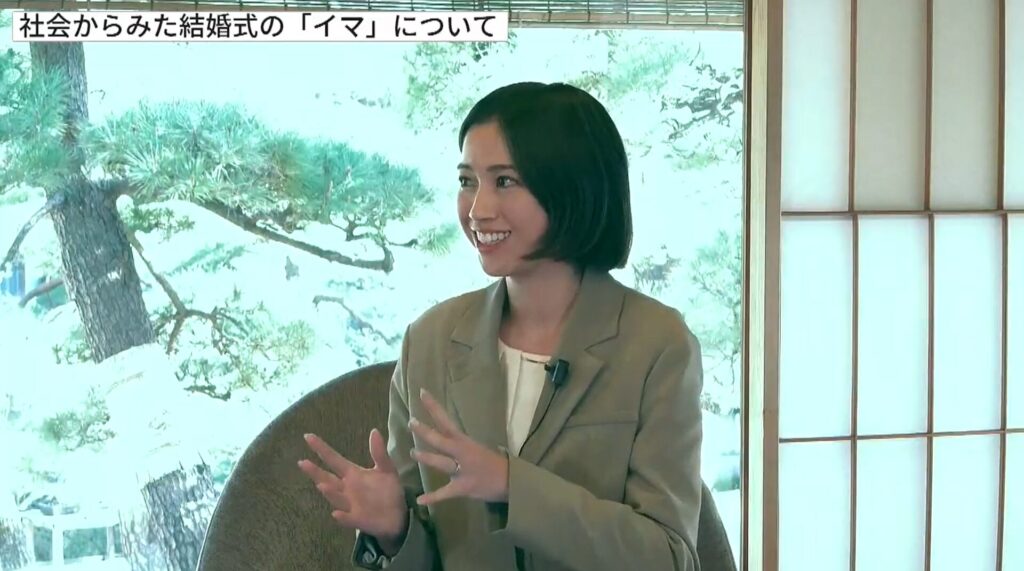
さらに、松尾は「ウエディングパークのクチコミでもハードの情報は多く入力されていますが、会場の理念やスタッフの思いといったソフト面を事前に伝えられるよう注力していきたい」と語りました。
費用面でのわかりやすさについて、mieruuparkではどう対応しているかと問われた松尾は、「ポイントは二つあります」と回答。
「ひとつはデータで見えることです。現状、見積もりの根拠が明確でないことが課題です。そこがデータで見えることで納得感が高まります。もうひとつは、選択肢をお見せすることです。結婚式当日の着地がどうなるかは、当日にならないとわかりませんが、不安になる一方で、お客様自身も100%見えることを求めているわけではありません。しかし、見えにくい部分を減らすことは可能です。例えば、シミュレーションの中で料理の選択肢やオプションを提示することで、よりわかりやすくできます」と説明します。
ただし、「それだけでは完璧に解決されるとは考えていない」と松尾。データやシミュレーションによる納得感を高めながら、次に向き合うべきは“結婚式の意味や質”だと指摘します。「写真だけでは伝わらない部分をお客様にわかりやすく伝えていくことは大きな課題です」と強調しました。
ちなみに、八芳園では事前に極力、現物に触れたり、一卓分のセッティングを作り試食したりする機会を提供しているそうです。関本氏は「選ぶときのわかりやすさを提示することで、納得感を高めています」と語りました。
結婚式が『四方良し』となるミライとは
今回のテーマは「結婚式が『四方良し』を叶えるためには」です。四方にはカップル、スタッフ、業界、社会が含まれます。業界で働く皆さんが幸せになるために、未来に向けて取るべきアクションとして、八芳園では昨年度、社内コンテストに同業者を招待しました。このコンテストでは、お客様や社内メンバーから高い評価を受けた社員やパートナーを称える取り組みを行っています。
金はこのコンテストが業界全体の成長につながる場としての役割を果たしていると述べ、「こうした取り組みは社員からの提案で始まることが多いのか、それとも経営陣が課題を見つけて主導する形で進めているのか」と尋ねました。
関本氏は「どちらのパターンもあります」と答えた上で、業界内の壁の問題を指摘しました。「学生時代には他社のプランナーとつながりがあっても、業界に入ると交流が途絶え、施設ごとに閉鎖的になりがちです。その結果、業界の課題が現場の人々に見えにくくなり、解決が進まないことが問題と考えています。」
また、それは若い人たちの業界離れにもつながる可能性があるとし、「『隠すものは何もない。全てオープンにして業界全体に貢献できることはどんどんやろう』と経営陣で方針を一致させ、さまざまな取り組みを進めている」と説明し、「業界全体でも急ぎ、取り組んでいかなければならない」と強調しました。
「解決に必要なのは共創であり、各社で動きを合わせる必要はないが、一緒に考え、一緒に取り組んでいくことが大切です。現場レベルで課題への取り組みが共有されなければ、解決されない」と語りました。

ちなみに、八芳園は、各地の文化や食材などにフォーカスするイベントの開催や、自治体との連携協定の締結などにも取り組んでいます。関本氏は、「課題を関係者全員で共有することが重要です」と話しました。現地に行くと、依頼者が提示する課題は真の課題ではないことがあるため、時間をかけて課題が何かを明確に共有することが“八芳園スタンス”だと語ります。
mieruuparkも株式会社テイクアンドギヴ・ニーズとの共創から生まれたサービスです。ウエディングパークとして大切にしていた点について松尾は「一緒に作り成し遂げていくために同じ目線になることを重視した」と話しました。「どういった状態をゴールとし、何を理想とするのかだけではなく、それが世の中にとって良い状態であるように描きたかった」と述べ、目線を同じにすることの重要性と難しさについて触れました。
また、松尾はウエディングパークがメディア側の視点を取っていたことに気づき、「今のブライダルフェアの接客方法や現場の方の気持ちについて解像度が足りなかった」とも語りました。さらに、結婚式のミライに向けて、他業界で当たり前になりつつある変化をウエディング業界へどう取り入れていくかが大きなテーマであると訴えました。
「例えば、保険業界ではネットで申し込みや手続きができ、LINEで完結することが一般的です。こうした状況が当たり前のお客様にリーチするためには、ウエディング業界もその仕組みを取り入れていかなければなりません」(松尾)
関本氏も「さまざまな業界の方々と事例を共有することで、糸口の部分の見え方が変わります。他業種であれば競合ではなく共創の関係になるため、取り組みやすい」と同調しました。
「内製すれば利益が明確に把握できますが、共創はプロセスが増えるため取り組みにくく、利益が上がりにくくなると思われているのではないでしょうか。しかし、事業者が単体でできることには限界があります。労働力や物流の問題を解決するためには、プロの皆さんと一緒に作っていく方が良いです。そのためにはお客様に価値観を伝え、ご納得いただける商品を作ることが重要です」(関本氏)。
松尾も「ウエディングパークだけでできることは限られている」としたうえで、「式場の皆様と共に作ることで、できなかったことが可能になりました。四方良しを叶えるのは非常に難しいですが、カップルにとって良いものから始まり、式場様にとっても良く、最終的には世の中のためにもなるところまでPDCAを回し、皆様と共に良いものを生み出していきたいです」とこれからの決意を述べました。

最後に、金が「結婚式が社会にとってどう変わっていくべきか、または何を守っていくべきかを考えるきっかけとなったら嬉しいです。ウエディングパークは『結婚を、もっと幸せにしよう。』という経営理念を通して社会意義を叶えていくために、今後も社会に向けてアクションを続けていきたいです」と締めくくりました。

 新サービス開発や組織づくりのリーダーに挑むU30パーソンの挑戦|Wedding-UP DAY 2023
新サービス開発や組織づくりのリーダーに挑むU30パーソンの挑戦|Wedding-UP DAY 2023  企業の競争力を高めていくために。事例とともに語る「デザイン経営」の在り方|「Wedding-UP DAY 2022」session1
企業の競争力を高めていくために。事例とともに語る「デザイン経営」の在り方|「Wedding-UP DAY 2022」session1  地域との共創プロジェクトを通して語る、これからの結婚写真|「Wedding-UP DAY 2022」session5
地域との共創プロジェクトを通して語る、これからの結婚写真|「Wedding-UP DAY 2022」session5