
Wedding AI Creators
2025.09.24
人、人生、社会を、もっと幸せに。ウエディングパーク「生成AI推進室」が挑む、業界の未来創造【Wedding AI Creators #1】
世界中で急速に進化するAI技術は、私たちの暮らしや働き方はもちろん、結婚・結婚式というかけがえのない体験にも、新たな可能性をもたらしています。結婚式のパーソナライズ、プランニングの最適化、魅力の伝え方、そして結婚式場とカップルとの新しい出会い方──。今、ウエディング業界はテクノロジーによる革新が求められる新時代へと歩みを進めています。
ウエディングパークは「結婚を、もっと幸せにしよう。」を経営理念に掲げ、「21世紀を代表するブライダル会社を創る」というビジョンのもと、創業から20年以上にわたり、インターネットやデジタル技術を活用した事業で業界変革を牽引してきました。
新連載 「Wedding AI Creators」 は、ウエディングの既存価値を単にAIで置き換えるのではなく、AIの力と人の想い・クリエイティブを融合させることで、ウエディングという体験を再定義し、新しい価値を創り出そうとしている挑戦者たちを紹介していきます。

今回は、2025年に発足した生成AIとウエディング業界をつなぐ業界初※の専門組織「生成AI推進室」の室長を務める株式会社ウエディングパークの岩橋聡吾さんにインタビューを実施。「AI×ウエディング」の意義や、テクノロジーで目指す未来について聞きました。
※国内のウエディング業界内における「生成AI」の専門組織として業界初(2025年7月 自社調べ)
■プロフィール
株式会社ウエディングパーク 生成AI推進室 室長 / BTO /エンジニアマネージャー 岩橋 聡吾(いわはし そうご)
2016年、株式会社ウエディングパークに中途入社。社内のセキュリティ周りを中心にエンジニアとして活躍。 2017年にシステムマネージャーとなり、2019年「Wedding Park AI Lab」所長、2020年5月「DX推進室」室長を務める。 その後、デジタルマーケティング本部やバリューデベロプメント本部での開発責任者も担い、2025年BTO(※)に就任。「生成AI推進室」を発足し、現在に至る。
※BTO(Beyo-nd Technical Officer):技術とデザインのウエディングパークをつくり、デザイン経営を加速させるための役職
業界初「生成AI推進室」を設立。業界変革を牽引してきたウエディングパークの新挑戦
――まず、岩橋さんのこれまでのご経歴とAIとの関わりのきっかけを教えてください。
岩橋:もともと、新卒から自動車メーカーで働いていました。車を量産するために、コスト面にも配慮しながら効率よく組み立てる生産技術という部門にいたのですが、Web業界にチャレンジしてみたくなり、一念発起して前職は受託開発と自社プロダクト開発の両方をしているスタートアップに入社したんです。そこでウエディング業界向けのサービスを提供していたし、親会社であるサイバーエージェントの案件を開発したこともあり、ウエディングパークに親近感を覚えたんですよね。そういったきっかけがあって、2016年に中途入社しました。
2017年にウエディングパークがAIを使ったマッチングサービスの開発と提供を始めたあたりから、私自身もAI周りの勉強をスタート、2019年には「AIラボ」の所長を務めました。AIとDXは親和性が高いということもあり、2020年5月に「DX推進室」の室長に就任。その後、デジタルマーケティング本部やバリューデベロプメント本部での開発責任者を担い、今年7月に「生成AI推進室」を立ち上げました。引き続きDX推進室の業務も担い、生成AI推進室の室長も兼任しています。
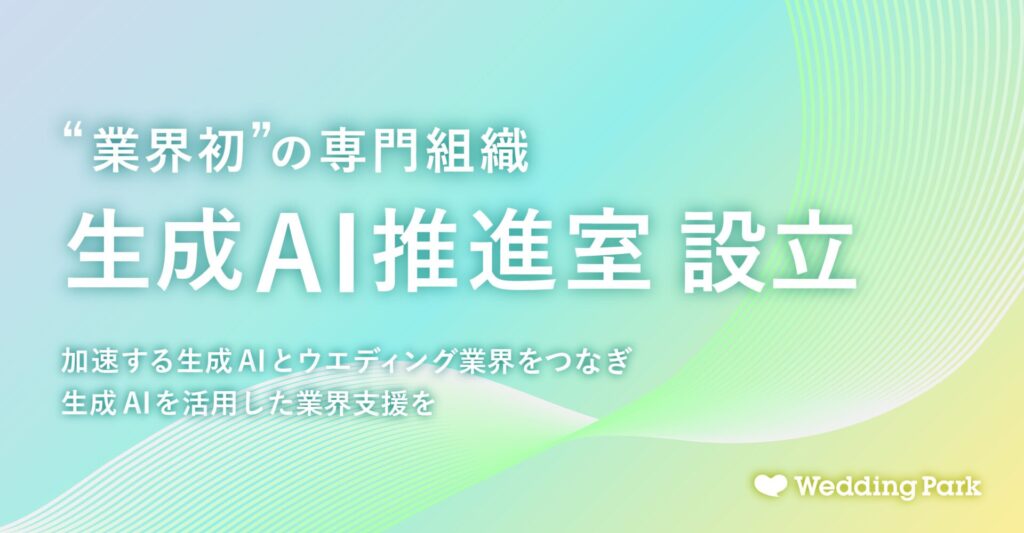
2025年7月に新設された「生成AI推進室」(プレスリリース)
――現在、岩橋さんは生成AI推進室の室長でありながら、「BTO」という役職にも就任されています。まず、BTOの役割を教えてください。
岩橋:BTOは「Beyo-nd Technical Officer」の略称です。弊社のロードマップである「技術とデザインのウエディングパーク」を創り、デザイン経営を加速させるための役職です。1年の任期の間に経営陣と共に仕事をし、事業統合判断、事業決裁なども行っています。
――今回「生成AI推進室」が設立された背景や目的について、詳しく教えてください。
岩橋:生成AIという言葉が日常的に使われるようになり、社会全体が変化している中で、ウエディング業界も例外ではありません。カップルとの接点や、サービスの提供方法においても、生成AIによって新たな可能性が生まれると考えています。
これまで、ウエディングパークは業界に対してさまざまなサービスを提供してきました。クライアントへの直販営業を通じて業界との強固なネットワークを築いており、現場の課題や状況を深く把握できることが私たちの強みです。この強みを活かし、生成AIを軸としたデザイン経営を推進することで、業界が抱える課題の解決を加速させたい——それが生成AI推進室設立の背景にあります。
また、親会社であるサイバーエージェントが日本における生成AIのリーディングカンパニーであることも、この取り組みを後押しする重要な要因のひとつです。

――具体的には、どういったことを推進していく部署なのでしょうか。
岩橋:生成AIの活用を弊社の強みにしていく部署です。生成AIを使ったプロダクトはすでに業界内外で数多く登場していますが、こうした技術は「点」の取り組みに終わりがちだと感じています。一部の専門性の高い人材がサービスやプロダクトを開発しても、組織全体で継続的に生成AIの価値を生み出し続けることが難しいからです。
そこで、まずは組織として生成AIの知見を蓄積し、活用スキルを高めていく必要があります。最終的な目標は、生成AIによってデザイン経営のサイクルを加速させることです。
現在一つの試みとして、生成AIによる生産性の力を借りながら、小さなチームを複数同時に立ち上げ、業務改善の糸口を見つける活動をしております。今後上手くいけば、これらを独立させて拡大していく計画を予定しています。
AI時代だからこそ、よりいっそう“オリジナルなウエディング”が求められる時代になる
――ウエディング業界が抱える課題に対して、AIを活用して具体的にどのような課題を解決しようと考えているのでしょうか。
岩橋:ウエディング業界には大きく分けて「人手不足」「少子高齢化」「結婚式実施組数の減少」「人員確保と給与UP」の4つの課題があるとされています。その中で深刻な人手不足に対応するソリューションとして、「おもレビAI」をリリースしました。
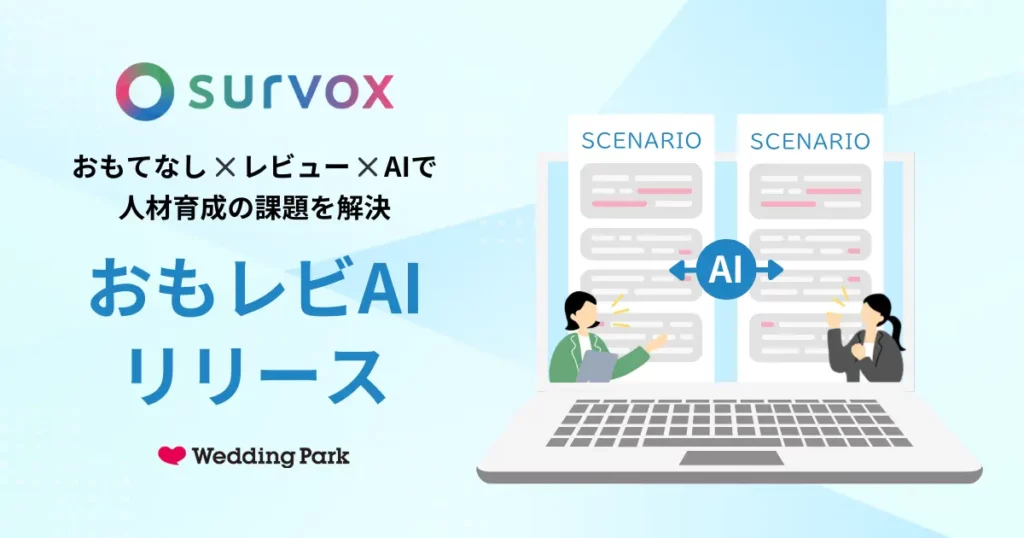
生成AIを活用し、人材育成課題を可視化「survox おもレビAI」(プレスリリース)
――「おもレビAI」で何が解決できるのか教えてください。
岩橋:結婚式場は限られた人員で日々の業務を行いながら、同時に毎年入社する新しいプランナーの育成も担わなければなりません。従来は、トップセールスのプランナーが新人の打ち合わせに同席してフィードバックを行い、育成していました。ところが、人手不足により同席する時間が確保できなくなり、若手プランナーがどのような接客をしているか把握することが困難になっている式場も出てきています。問題が表面化するのは、成約率や単価といった数字が下がってからというのが現状です。
こうした課題を解決するためにリリースしたのが「おもレビAI」です。このシステムでは、トップセールスプランナーの接客や打ち合わせをAIが言語化・構造化してシナリオを作成。学習者はそのシナリオに対して接客のシミュレーションを行い、「トップセールスならこう対応するが、あなたにはここが不足している」といったフィードバックをAIから受けることができます。
このようなセルフエデュケーションにより、一定レベルまで自己成長が可能となり、おもてなしの品質を高い基準で均質化するAI活用を実現していきます。

――AIが人の育成やおもてなしに関わることに対して、「人間らしさが失われるのでは」という声や「AIが仕事を奪うのでは」といった声も上がりそうですが、岩橋さんはAI時代における人の役割をどのように考えていますか?
岩橋:汎用的な業務はAIが担う一方で、人のクリエイティビティはこれまで以上に重要になると考えています。
なぜなら、生成AIは結局「何かのコピー」でしかないからです。しかし、カップルが本当に求めているのは、これまでにない新しい体験なんですね。そうした体験を創り出すためには、人がクリエイティブなことを考える時間をしっかり確保する必要があります。
最近はコスパやタイパが重視され、手間暇をかけなければならないことが削ぎ落とされる傾向にあります。でも、その先に本当に価値のあるものが残るのか、と言われると、僕は疑問に思うんですよね。生成AIが作るコピーや画一的な結婚式ではなく、式場とカップルだからこそ生み出せるオリジナルなウエディングが今後よりいっそう求められると思うんです。
だからこそ、ウエディングパークはカップルにより深く寄り添い、特別な体験を創り出すための時間を確保する。その手段として生成AIを活用していきたいと考えています。
――こういったお話をうかがうと、岩橋さんの結婚式に対する想いの強さを感じます。
岩橋:もしかしたら自分の経験が大きな原動力になっているのかもしれません。僕は約10年前に結婚式を挙げました。振り返ってみると、あれほど多くの親しい人が一堂に集まって、みんな笑顔で「おめでとう」と言ってくれる瞬間って、今振り返ってみても人生で結婚式だけだったんですよね。
当時は準備に手間暇がかかると感じていましたが、今となってはその体験が頭の中にしっかりと刻まれています。ときどきあの日の光景を思い出すこともあるほど、自分にとって特別な体験でした。
こうした体験はアナログかもしれませんが、人生において非常に大切なものだと思います。最近よく聞く「時短」や「タイパ」という言葉は、正直あまり好きじゃないんですよね。効率だけを追求した先に、本当に人生を豊かにするものが残るのでしょうか。
手間暇をかけても、結婚式やおもてなし文化を次世代に継承していきたい。自分の子どもにもぜひ体験してもらいたいと思っています。そうした大切な体験を残しながら、同時に現場の課題も解決できる、そんな生成AIの使い方を示していきたいですね。
「AI×ウエディング」でこれまで以上にカップルに寄り添った結婚式を実現したい
――これから先ウエディングパークが描く「AI×ウエディング」の今後の展開や目指す未来を教えてください。
岩橋:生成AIを活用してデザイン経営を加速させ、業界全体に良い影響を与えていきたいと考えています。ただし、現時点では組織内の生成AI活用はまだ発展途上です。まずは生成AIを使いこなせる組織基盤をしっかりと構築することから始めたいと思います。
その上で重要なのは、業界の声や現場のフィードバックを丁寧に聞きながら開発を進めることです。試作品を実際に使っていただく中で、私たちだけでは気づけない課題や、現場ならではの工夫が数多く見えてきます。過去には「良いもの」を作ったつもりでも、現場の運用に馴染まず浸透しなかったプロダクトもありました。だからこそ、業界の皆さんと二人三脚で開発を進め、実際の現場に適したサービスを共に作り上げていくことが不可欠だと考えています。
最終的に、私たちが提供するサービスに生成AIを直接組み込むかどうかは状況次第です。しかし、生成AIをはじめとするテクノロジーの力を借りながら、これまで以上にカップルに寄り添った結婚式を実現し、おもてなし文化を次世代に継承できるようなサービスを業界に提供していきたいですね。

※取材対象者の所属、役職および掲載記事の内容は取材当時のものです
取材:大井あゆみ / 文:田中いつき
写真:伊藤メイ子
企画編集:ウエディングパーク

 生成AIは式場探しの“提案者”ではなく“支援者”。Wedding Parkが「偶発的な出会い」で目指す、四方良しの未来【Wedding AI Creators #2】
生成AIは式場探しの“提案者”ではなく“支援者”。Wedding Parkが「偶発的な出会い」で目指す、四方良しの未来【Wedding AI Creators #2】  ウエディング業界のAI時代を創る挑戦者たちを追う新企画「Wedding AI Creators」をスタート
ウエディング業界のAI時代を創る挑戦者たちを追う新企画「Wedding AI Creators」をスタート